メバルとは、「メバル科メバル属」に属し名前が「○○メバル」となる魚の総称のことを言います。
例えば白メバル、黒メバル、赤メバルをはじめウスメバルやトゴットメバルなどは、まとめて「メバル」と呼ばれるということ。
少し昔の話ですが、「白、黒、赤」のメバル3種は全て同じ1つの魚だと思われていて、標準和名「メバル」が当てられていました。このことは「白メバル、黒メバル、赤メバル」のメバル3種が、数多いメバル類の中で最もポピュラーな種類であることと、近縁種の見分けがしづらい魚類群であることを表しています。
メバル属の魚は外見の似た魚が多く、全部を覚えることは至難の技。見た目そっくりなので見分けがつかず、単に「メバル」と呼ばれることが多いのです。

今回は、広い意味で「メバル」と呼ばれる魚の特徴を紹介していきます。
メバルとは?特徴や似た魚
メバルは、北海道から九州までの温帯の沿岸に住む底生魚で、だいたい浅い海の底の方に生息しています。
磯魚の代表的な魚として「クロソイ」が挙げられますが、メバルも負けず劣らず磯魚界では主役級の存在。
防波堤から釣りをすれば、季節問わずに釣れる確率の高い魚の一つです。
同じメバルでも、黒メバルや白メバルに比べやや外洋に生息するのが赤メバル(別名「沖メバル」)であるなど、メバルの中でも細かく見ると微妙に性質が異なったりするようです。
全長は成魚でも25〜35センチくらいの小型魚が多く、卵胎生で産卵期は12月〜2月頃です。(「卵胎生」は、お腹の中に卵を持ち孵化もお腹の中で行われるという特性のこと)
メバルに似た魚
メバルはこれといって大きな特徴のない平凡な魚ですが、以下のポイントはメバル特有のものと言って良いでしょう。
- 目が大きい
- 受け口である
- 各部のヒレが大きい
平凡な魚だから似た魚もたくさんいて、同じメバル科のカサゴなどはその代表。
一方で、メバル属のマゾイやクロソイは、メバルではなく「ソイ」と呼ばれることが多い魚ですが、“メバル”と呼んでも間違いではなく、実際「マゾイ」は通称で標準和名は「キツネメバル」と言います。しかし、関東ではソイは「ソイ」。メバルと呼ぶのはあまり聞いたことはありません。
また、メバルはサイズの小さい魚であるため他の魚種の幼魚と間違われることも多いです。例えば、「ハタ科の魚」とも似ています。しかしハタ科の多くは大型化し、比較的南の海に生息するためカラフルな紋様があることが多いので、よく観察すればメバルとハタ科の魚は見分けられるでしょう。
ハタ科と似た特徴の一つは、メバルは堤防でも釣れる魚なのに目がデカいということ。
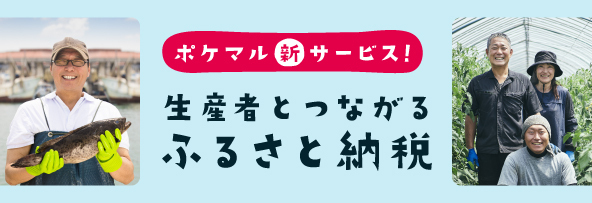
メバルは目が大きく視力が良い
これと言った特徴の少ないメバルにとって、目の大きさはひとつのポイントと言えそうです。

深海魚じゃないのにギョロついた目をしていて、実際に視力も良い。
夜行性である証拠と言われています。
メバルに使う釣り糸は、見切られないように細めにする必要があるそうです。メバルの仲間は総じて目が大きくて視力が良いのです。
メバルは「受け口」
メバルの口は、典型的な魚らしい形をしています。

- 「受け口」である
- 唇は薄め
- 歯が細かくて短い「繊毛(せんもう)」のような形状
いろんな魚の口を注意深く見ると、「受け口」であるケースが多いことに気づきます。
魚類を全体的に見ても「受け口の魚」が多数派と言えそうです。
メバルも受け口。
しかし、なぜ受け口なのかというと、ざっくり言えば「獲物をもれなく食べられるように」です。
人間みたいに器用に使える手が魚にはありませんから、ひと噛みで獲物を確実に食べなければならないということでしょう。
メバルの唇は薄い
魚の口は「吻(ふん)」と呼びます。
正確には口を含む周りのことを「吻」と呼び、先っちょ(つまり唇)を「吻先」と言います。
そもそも、魚の唇っぽい見た目の部位は、人間のそれとは成り立ちが違うようです。人間の唇、魚の唇(のような部位)、それぞれ本来の役割というのは、実はよく分かっていません。

魚は「餌をより食べやすく」することが、口(吻)の形の進化に繋がっていると思います。
メバルの唇が薄いのは、砂泥の中に顔を突っ込んでまさぐったり、岩肌をこそいだりする必要が無いためだと個人的には思います。
特殊な食性を持つ魚(コブダイのように)の吻は、変わってることが多いですからね。
メバルの歯は細かい繊毛状
メバルの歯は、”うぶ毛”のように見えますが、実際に触ってみるとザラザラとしていて荒い紙ヤスリのようです。
これは肉食である魚の証拠と言えるでしょう。
歯の形状から想像するに、メバルが食べる獲物は体がそこまで硬くなくプランクトンのような小さな生物とも違うと想像できます。
実際、オキアミやごく小さな小魚、小さいイカなどを食べています。
鋭い歯は不要だけど、獲物をしっかり捕まえる細かい歯は必要ということでしょう。
弱肉強食の海の世界では、取りこぼしを少しでも減らすために、口の形や大きさは様々に進化しています。
ちなみに黒メバルの口の写真をよく見ると、下アゴの先端はポコっと突起がありますよね。もしかしたら何かしらの獲物を捕まえるのに都合の良い形なのかもしれません。
地味ですが、ちょっと不思議なメバルの口の紹介でした。
メバルの別名、メバルの種類
厳密に言えば「メバル」という種の魚はいません。
メバル属に分類される赤メバルや白メバル、黒メバルの総称として、「メバル」という言葉が使われています。
総称である「メバル」という言葉の代替は、「メヌケ」、「ソイ」、「赤魚」、など。・・とは言え、あまり一般的じゃなく通じないケースがあるかもしれません。
「メバル」としてまとめて語られがちな、個別の種にも注目してみます。
カサゴ目フサカサゴ科(あるいはメバル科)メバル属には、本記事で紹介している黒メバルの他に「赤メバル」、「白メバル」も属しています。他にマゾイやクロソイなども。
見た目はとてもよく似ていて正直見分けがつきにくいですが、体色がそれぞれの名前の通りの色合いとなっていることで見分けることができます。
冒頭でも書きましたが、この3種は最近まで1つの種と見なされていました。
体色の違いは、住む環境によって変わる保護色のようなものと考えられていたらしく、研究が進み、今では別々の種として数えられることになったのです。
黒メバル、白メバルが岩礁域で多く見られるのに対し、赤メバルはやや沖合に生息するようです。
「春告げ魚」と呼ばれる
「白、黒、赤」の3種のメバルたちは、まとめて「春告げ魚」と呼ばれます。
つまり春の代表的な魚。
「春告げ魚」はメバルの他にもいて、「ニシン」などの魚も春の代表的な魚とされています。
それどころか、地域によって「春告げ魚」の定義は変わってきます。
筆者的には、春の代表的な魚はメバルじゃないかという気がしています。
メバルの食べ方は「煮付け」
メバルと言えば煮付けが有名です。
身離れがよく、火を通しても固くならない上に、アラから良い出汁がでるので煮物にぴったり。
サイズも小さいので、丸のままの煮付けが良いでしょう。
あるいは刺身も十分美味です。上品な白身で真鯛などの系統に近い味わいは高級魚として扱われることも多いです。
刺身にはより大きいサイズのメバルが適しています。
大型になれば味が悪くなる魚がいる一方、メバルなどはサイズが大きいと味も良くなり価値も上がります。
特大サイズのメバルは高級品で大衆魚の枠を超えますが、入手は困難です。

コメント