納豆は、赤ちゃんの離乳食として食べさせてあげたい食材のひとつです。なぜなら栄養面でパーフェクトだから。
タンパク質や食物繊維だけでなく、脂質、ビタミン、ミネラルなどなど、そしてなんと言っても唯一無二の「納豆菌」は血液の循環や肌ツヤにも効果アリとされています。
しかし、納豆の風味を赤ちゃんは受け入れてくれるのでしょうか?
少しハードルが高いような気もします。
今回は、「赤ちゃんの離乳食」としての納豆を紹介していきます。
【納豆の離乳食】そのまま食べる?タレは入れる?
赤ちゃんへの離乳食に適した食材である、「納豆」。
子供からお年寄りまで一生涯、食べるべき理由はたくさんあります。
- ニキビ治療をはじめ、美容(肌)に良い
- ダイエット食品として支持されている
- 中性脂肪の増加を抑える
- 血圧を下げる、血液をサラサラにする
- 生活習慣病(がん、糖尿病など)予防に効果的
世の中には「菌活」や「腸活」などの言葉もあり、発酵食品である納豆を食べることは、「第二の脳」とも呼ばれる腸へプラスの効果をもたらすでしょう。
今回は離乳食としての納豆に着目。
食べてくれさえすれば、赤ちゃんの成長の助けになることは間違いありません。問題は、食べてくれるかどうか・・・。
【納豆離乳食】食べさせ方
「人間の腸内環境(腸内フローラ)は幼い頃にだいたい決まる。」と良く言われます。
赤ちゃんの頃から菌活をスタートさせるには、まさに「納豆」というわけですね。栄養豊富で食感も柔らかい納豆は、まさに離乳食向けと言えます。
そもそも「納豆を赤ちゃんに食べさせても大丈夫なの?」と心配になりそうですが大丈夫です。
ただし、大豆アレルギーだけは注意してください。
食べさせ方のポイントをまとめました。
- 目安は離乳食中期(生後7、8ヶ月後)から。
- ひきわりタイプを使う。
- 味付けはしない(タレは入れない)。
- ネバネバや匂いを抑える工夫をする(加熱、細かく)
- 好きな食べ物に混ぜて様子を見る。
- 大豆製品なので、アレルギーには気をつけて。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
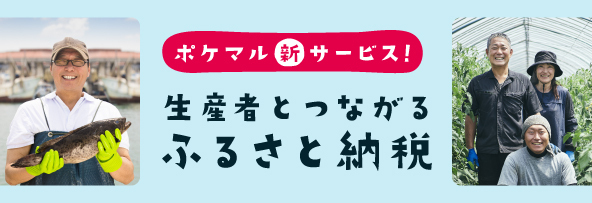
【離乳食のコツ】“ひきわり”を味付け“ナシ”で
ひきわりタイプよりも粒タイプのほうが栄養価が高いイメージですが、粒タイプには皮が付いており、赤ちゃん目線だと「食べにくい」と感じてしまうかも。
そもそも食べてもらえないと意味がないので、ひきわりタイプのほうが無難だと思います。
ひきわりタイプでも、さらに細かく刻むなどの工夫をすればより食べやすくなるでしょう。
納豆パックに付属のタレは使いません。
タレには人工甘味料が使われていて体に悪いと言われますが、微々たる量なので大人であれば大量に接種しなければほぼ問題ないでしょう。
赤ちゃんにはもう少し繊細に接したいところなので、タレは使わないほうが良いですし、そもそも濃い味付けは食育にも健康にも悪いので避けるべきです。
【離乳食のコツ】ネバネバと臭みを抑える
ネバネバや匂いは赤ちゃんに「不快」と取られがち。湯通しするなどしてネバネバと匂いをなるべく取り除きましょう。
注意点は、煮込まないこと。
煮込むと納豆の旨味が損なわれ、しかも臭みが薄まるどころか強調されます。自分でも食べてみると分かりますが、美味しくないです。
さらに、肝心の栄養も落ちてしまいそうですし。
臭みを取るのにオススメの方法は炒めること。臭みが香ばしさに変わります。軽く炒めるだけでも、劇的に臭みは軽減します。
ただし、納豆キナーゼは熱に弱いので本当ならばそのまま食べさせたいところです。
そのまま食べさせるのは、離乳食後期(月齢9〜11ヶ月くらい)であれば、様子を見ながらトライしても良いでしょう。軽くレンジで温めてからが良いと思います。
納豆の独特の風味やネバネバは、大人でも苦手な人がいます。赤ちゃんにはもっとハードルが高いと思うので、例えば、普段よく食べる好きな食事に少し混ぜるなどの工夫は効果的かもしれません。
【大豆アレルギーは必ずチェック!】“豆腐”を少量から
赤ちゃんのアレルギーの症状は、唇の腫れ、発疹、せき、呼吸困難など多様な種類があります。
赤ちゃんはまだ体が未成熟であるため、上記のような症状が出てもそれがアレルギー由来なのかは判断が難しいです。
気になる症状は、自己判断せずお医者さんに相談するのが良いでしょう。
大豆アレルギーは、納豆の前にまず豆腐から食べさせて様子を見るほうが良いでしょう。
最初は少量から。絹ごしを加熱して提供すると良いです。
納豆に含まれる栄養素まとめ
赤ちゃんが納豆を嫌がらないのであれば、離乳食の献立に積極的に組み入れたいところです。
納豆の栄養素と、期待できる効果をまとめてみました。
| 栄養素 | 期待できる効果 |
| イソフラボン | 骨粗しょう症予防、アンチエイジング効果 |
| ナットウキナーゼ | 血管にできる血栓を溶かす |
| 食物繊維 | 整腸作用、生活習慣病予防 |
| レシチン | 細胞が栄養を取り込むのを助ける、生活習慣病予防 |
| ミネラル | 骨や歯を健康に保つ |
| ビタミン | 疲労回復、カルシウムの吸収を助ける等 |
| 大豆サポニン | 中性脂肪の吸収を抑制する |
| 大豆ペプチド | 疲労回復、コレステロール低下 |
| 大豆たんぱく | 体を作る基本の栄養素 |
| 脂質 | 体を動かすエネルギー |
| 炭水化物 | 思考力の維持、筋肉の維持 |
注目すべきは「イソフラボン」や「ナットウキナーゼ」で、効果のほどはもうすでに説明した通りですが、そんな希少な栄養素を摂取できるというだけでも、納豆を食べる意味はあるのではないでしょうか。
赤ちゃんは本能的な味覚や嗅覚で、大人よりも食べる/食べないをよりハッキリ判断するので、「納豆、イヤ!!」となったらアウトです。離乳食として納豆を食べてもらうには、本能的に敬遠しがちな「臭みとネバネバ」をなんとか和らげる工夫を施しましょう。
もちろん、「味覚」としての納豆の魅力も忘れてはいけません。納豆のさらなる加工品についても紹介しています。


コメント